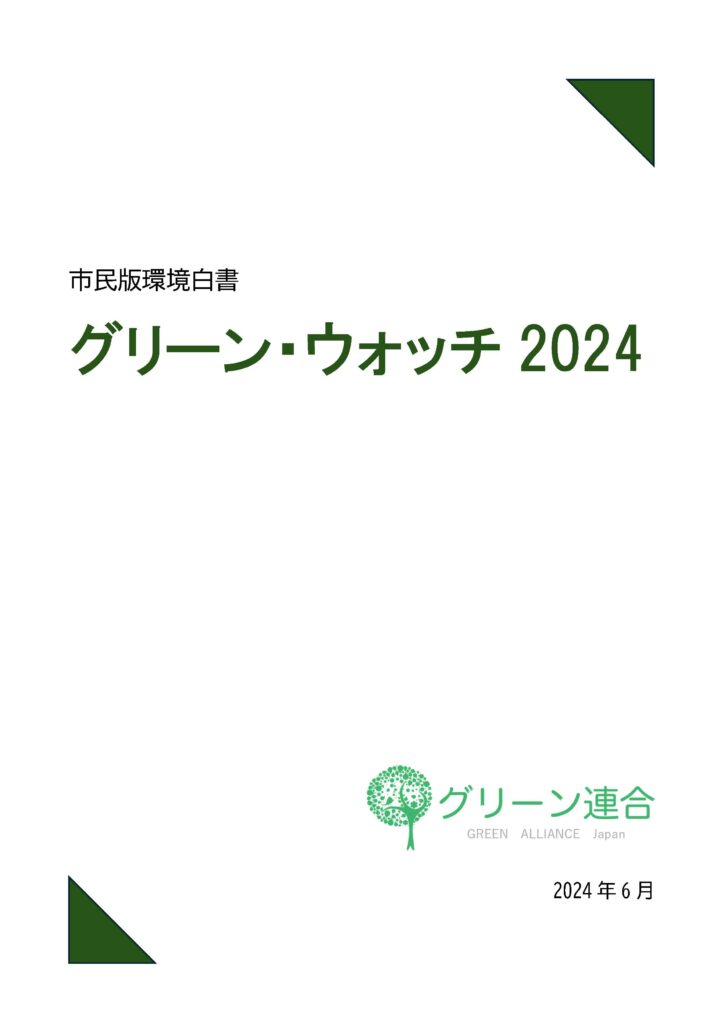市民版環境白書2025グリーン・ウォッチ
2025年6月発行
グリーン連合は、政府とは異なる市民の視点から環境の現状や問題点を分析し、より良い解決の方向性を示すことを目的に、 『市民版環境白書グリーン・ウォッチ』を2016 年の設立以来、体制の見直しを受けて休刊となった2022 年を除き毎年、発行しています。幹事を中心に編集委員会を組織し、会員団体メンバーを中心に執筆 ・編集を行い、気候変動・エネルギー問題、化学物質問題、原発問題、生物多様性など主要な環境問題を解説、また関連政策をレビューしています。
2025 年版では、脱炭素社会の実現に向けた政策や再生可能エネルギーの進展、プラスチック汚染やPFAS 問題への対応、生物多様性条約COP16 の成果などを詳しく解説します。そして、市民の力で社会を変える具体的な方法として、環境政策への市民参加の仕組みづくりや、民主主義によるイノベーションの必要性について取り上げています。特に今回は、行動する市民の声を紹介しています。若者による気候訴訟、お店のプラスチック容器についての市民調査、気候市民会議、生物多様性に関する若者グループなど、各地で実践されている取り組みが示すのは、「一人の行動が社会を動かす」ことの現実です。また、10 周年を迎えたグリーン連合の活動の歩みを振り返る特設コーナーを設けています。
環境問題は私たちの暮らしに密接に関わるため、市民の理解と協力なしには解決できません。『グリーン・ウォッチ』が、環境をめぐる現状を伝えるだけでなく、日々の生活の中でできる小さな一歩と経済や社会の仕組みを変える第一歩につながることに目を向けるきっかけになれば幸いです。
市民版環境白書2025グリーン・ウォッチ
目次
はじめに
第1 章 脱炭素社会実現に向けた最新動向 ……………………….. 1
第1 節 気候危機の現状と課題 ……………………………….. 1
(コラム)仕組みを変えるために行動する若者グループからのメッセージ
<気候変動> ……………………………………. 10
第2 節 脱炭素化に向けた再生可能エネルギーの取り組み ………….. 12
第2 章 東京電力福島第一原発事故処理と原子力政策の現状 …………. 19
第3 章 化学物質とプラスチック ………………………………. 26
第1 節 プラスチック汚染の現状と課題 ……………………….. 26
(コラム)市民調査で気づきから行動へ
~「お店のプラスチック調査2024」の結果から …………. 33
第2 節 食品安全委員会・PFAS リスク評価の問題点 ………………. 35
第4 章 生物多様性条約COP16 の成果と市民社会への示唆 …………… 38
(コラム)仕組みを変えるために行動する若者グループからのメッセージ
<生物多様性> ……………………………………… 43
第5 章 身近なアクションから仕組みを変える行動へ ………………. 45
第1 節 環境問題の解決になぜ民主主義のイノベーションが必要なのか .. 45
(コラム)気候市民会議の効果と参加者の声(厚木市民発電所) ……. 50
第2 節 日本で環境政策への市民参加の仕組みをつくろう ………….. 52
第3 節 民主主義につながる環境教育を ……………………….. 59
10 周年を迎えたグリーン連合 活動の歩み ………………………. 63
活動年表 ……………………………………………….. 63
会員団体数の推移 ………………………………………… 67
表紙イラストで見る「市民版環境白書 グリーン・ウォッチ」 ………. 69
グリーン連合活動記録 ………………………………………. 71
グリーン連合会員名簿 ………………………………………. 76
グリーン・ウォッチ編集委員会・奥付